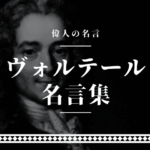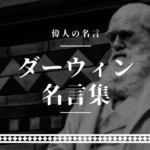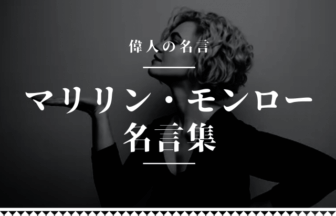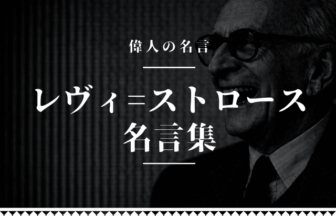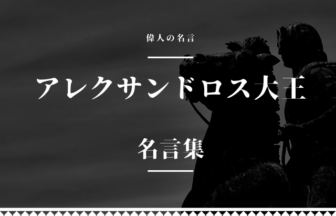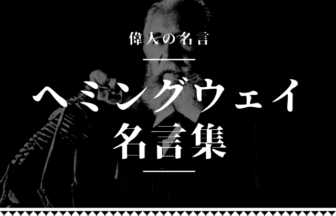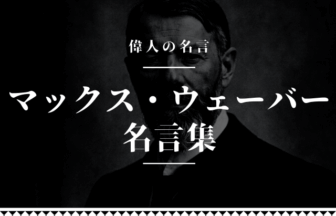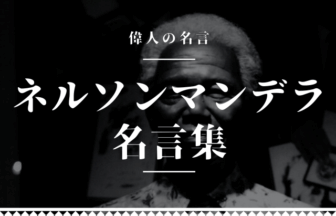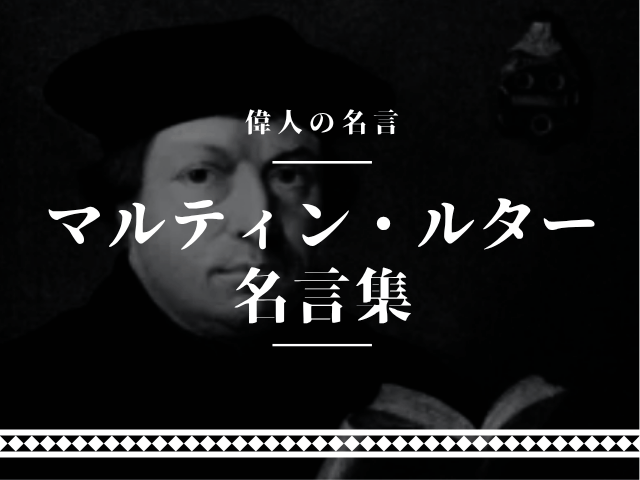
この記事では、『マルティン・ルターの名言』を厳選して紹介しています。
マルティン・ルターの名言には「たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植える。」や「死は人生の終末ではない。生涯の完成である。」など、心に響く名言が多数あります。
ドイツの宗教改革者で、旧来のカトリック神学を根底から批判する九十五ヶ条の論題を公表し、宗教改革の端を開いた、マルティン・ルターの名言をご堪能ください。
本記事は広告を含みます。
目次
マルティン・ルターはどんな人物?
名前:マルティン・ルター(Martin Luther)
誕生:1483年
没年:1546年
国籍:ドイツ
職業:宗教改革者
名言:「たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植える。」「死は人生の終末ではない。生涯の完成である。」など
マルティン・ルターはドイツの宗教改革者で、罪から逃れえないことに苦しみましたが、人間は善行によってではなく、神の恵みによりただ信仰によって義とされ救われることを悟りました。
教会の贖宥状乱売に憤り、その基礎にある旧来のカトリック神学を根底から批判する九十五ヶ条の論題を1517年に公表し、教皇の破門を受け、宗教改革の端を開きました。
1522年に聖書のドイツ語訳を行い、自ら多くの讃美歌を作りました。
マルティン・ルターの名言32選【心に響く名言|宗教改革・りんご】
ここからは、マルティン・ルターの名言を厳選して紹介していきます。
たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植える。
マルティン・ルターの名言
死は人生の終末ではない。生涯の完成である。
マルティン・ルターの名言
我々は生の真っ只中にあって、死に取り囲まれている。
マルティン・ルターの名言
希望は強い勇気であり、新たな意志である。
マルティン・ルターの名言
全てのことは願うことから始まる。
マルティン・ルターの名言
心から信ずることによって、人間は正しく、また義とせられる。
マルティン・ルターの名言
恋なき人生は死するに等しい。
マルティン・ルターの名言
「今でなくても」が、「ついにとうとう」になることは実にはやい。
マルティン・ルターの名言
酒と女と歌を愛さぬ者は、生涯馬鹿で終わる。
マルティン・ルターの名言
家庭は、民族の幸運と不運の源泉である。
マルティン・ルターの名言
薬は病気の人間を、数学は悲しむ人間を、神学は罪深い人間を生む。
マルティン・ルターの名言
私は聖書の中にただ、十字架に付けられたキリストのみを理解する。
マルティン・ルターの名言
私の良心は神の言葉の中に捉えられている。
マルティン・ルターの名言
自説を取り消すことはできない。
マルティン・ルターの名言
ひとつの嘘を本当らしくするためには、いつも七つだけ嘘を必要とする。
マルティン・ルターの名言
嘘は雪玉のようなもので、長い間転がせば転がすほど大きくなる。
マルティン・ルターの名言
慈悲を与える時の、婦人の心情より柔和なものは世界上にない。
マルティン・ルターの名言
神はわれわれの砦である。
マルティン・ルターの名言
神がその人を通じてある偉大な行為を望むかのように、誰でもが行動するべきである。
マルティン・ルターの名言
良い結婚よりも、美しく、友情があり、魅力的な関係や団体、集まりはない。
マルティン・ルターの名言
酒は強く、王はもっと強く、女はそれよりさらに強く、けれども、真理は最も強い。
マルティン・ルターの名言
神の言葉がもはや予言しないようになるところでは、人々は野蛮になるだろう。
マルティン・ルターの名言
神の道は、後ろからだけ読むことができるヘブライ語の本のようなものだ。
マルティン・ルターの名言
今日はすべきことがあまりにも多いから、一時間ほど余分に祈りの時間を取らなければならない。
マルティン・ルターの名言
私がここで放屁をすると、ローマではそれが芳香を放つ。
マルティン・ルターの名言
我はここに立つ。他になしあたわず。神よ我を救いたまえ。アーメン。
マルティン・ルターの名言
喜びについて信仰が不足していることを私たちは知ることができる。強く信仰するなら、また必ずや強く喜ぶに違いないのだから。
マルティン・ルターの名言
私がここに座って、うまいヴィッテンベルクのビールを飲む、するとひとりでに神の国がやってくる。
マルティン・ルターの名言
私は話すとき、自分を最も低く引き降ろす。聴衆のうちインテリを見ないで、子供を見て話をする。
マルティン・ルターの名言
いくら知恵があっても、これを使う勇気がなければ何の役にも立たないように、いくら信仰が厚くても、希望がなければ何の価値もない。希望はいつまでも人とともにあって、悪と不幸を克服するからである。
マルティン・ルターの名言
平安はいかなる権利にもまして貴重なものである。平安が権利のためにではなく、権利が平安のために作られているのだ。したがって、どちらかが道を譲らねばならないとしたら、権利が平安に譲らねばならないのであって、平安が権利に、ではない。
マルティン・ルターの名言
この世を動かす力は希望である。やがて成長して新しい種子が得られるという希望がなければ、農夫は畠に種をまかない。子供が生まれるという希望がなければ、若者は結婚できない。利益が得られるという希望がなければ、商人は商売にとりかからない。
マルティン・ルターの名言
マルティン・ルターの本・関連書籍を紹介
ここからは、マルティン・ルターのおすすめの本や関連書籍を紹介します。
マルティン・ルターの本おすすめ①:マルティン・ルター ことばに生きた改革者
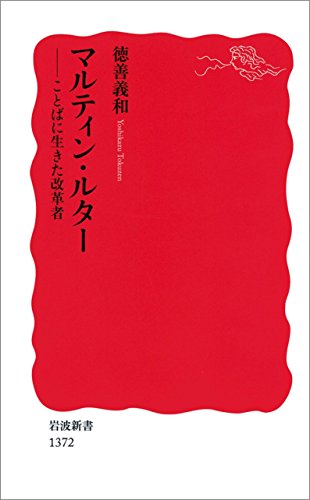
マルティン・ルター-ことばに生きた改革者 (岩波新書)
『マルティン・ルター ことばに生きた改革者』は、宗教改革者マルティン・ルターの思想と行動を「ことば」の力を軸に描いた伝記的研究です。
著者は、ルターが聖書のドイツ語訳を通して信仰を民衆のものとし、言葉によって宗教と社会を変革した点を強調します。
また、ルターの内面的葛藤や信仰への誠実さを通して、個人の自由と良心の尊厳を追求した姿を浮き彫りにしています。
マルティン・ルターの本おすすめ②:キリスト者の自由・聖書への序言
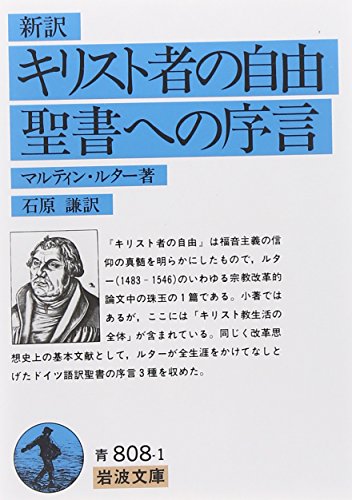
キリスト者の自由・聖書への序言 (岩波文庫)
『キリスト者の自由・聖書への序言』は、マルティン・ルターによる宗教改革思想の核心を示す重要な著作です。
ルターは「信仰による自由」を説き、キリスト者は信仰によって罪から解放され、神の前では自由である一方、隣人への愛によって奉仕する義務を負うと主張します。
また、「聖書への序言」では、聖書を信仰の唯一の基盤と位置づけ、教会権威に依存しない個人の信仰理解の重要性を説きます。
マルティン・ルターの本おすすめ③:宗教改革三大文書 付「九五箇条の提題」
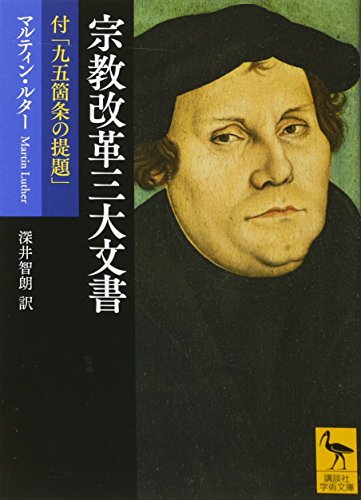
宗教改革三大文書 付「九五箇条の提題」 (講談社学術文庫 2456)
『宗教改革三大文書 付「九五箇条の提題」』は、マルティン・ルターが宗教改革の思想を体系的に示した重要文書を収録しています。
教会の権威や免罪符の乱用を批判し、「信仰による義」「聖書中心主義」「万人祭司」を主張することで、信仰と救済を個人の内面に取り戻そうとしました。
「九五箇条の提題」では、贖宥状批判を通じて教会改革を求め、信仰の自由と良心の自立を訴えます。
そのほかの偉人の名言はこちらをどうぞ。
⇒偉人の名言一覧